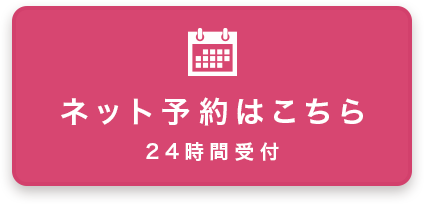


頭痛でお困りの方へ(頭痛外来)
「頭痛」と言うと、重大な病気ではない・軽いイメージを持たれてしまうことがあります。頭痛で仕事や学校を休むと、他の人から「怠けているのでは?」と誤解されることも少なくありません。
しかし実際には、「頭痛があると、寝込んで何も手につかない。」「頭痛の時、吐き気や嘔吐のため薬を飲むこともできない。」「頭痛がいつおきるか分からないので、大事な予定が立てられない」など、頭痛によって生活に支障をきたしてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
実は「日本頭痛学会」というのがあり、頭痛は立派な病気です。 個々の頭痛に診断名があります。日本頭痛学会トップページ│日本頭痛学会
院長はこの頭痛学会の専門医です。
(2025年現在世田谷区で6人いますが、院長はそのうちの1人です)認定頭痛専門医一覧│日本頭痛学会
また脳神経疾患のスペシャリスト(神経内科専門医)であり、頭痛をトータルに診断・治療します。
● 当院には下記のような悩みを持った方が、多く来院されます。
- 頭痛がひどく、仕事・学校・家事などに支障がある。
- 市販薬では痛みが治らない、市販薬を頻繁に飲んでいる。
- 頭痛があると、吐き気や嘔吐のため薬を飲めない。
- 頭痛がいつ起きるかわかないため、大切な予定が立てにくい。
- 試験前や大事な仕事の時に、頭痛が起きにくくしたい。
- 何が原因で頭痛が起きているのかを調べたい、知りたい。
このような悩みを当院で一緒に解決してければと思いますので、諦めずにご相談下さい。
当クリニックの頭痛外来の特徴
- 頭痛診療かつ脳神経疾患の専門医が、より適切な診断・治療を行います。(対象患者:中学生以上です。)
- 我々は、頭痛で患者さんが困っている事柄を共有し、それを少しでも解決できるように診療していきます。
- 入院や手術などが必要な頭痛は、信頼できる医療機関にご紹介いたします。

実際の診療方法
当クリニックでは以下の流れで診療してまいります。
診療時は、頭痛発作がない時でも大丈夫です。
□頭痛診療の流れ
-
診断
問診、診察。必要に応じて血液検査、脳画像検査を行い診断。
手術や入院が必要な場合は、病院などへ紹介。
それ以外の方は、当院で治療を開始。 -
治療
頭痛があるときの頓服薬「急性期治療」。
並行して、頭痛ダイアリーによる頭痛の頻度、急性期治療の評価。
頭痛の頻度が多い、急性期治療での治療効果が乏しい場合は「予防治療」を検討。
① 診断
頭痛は立派な病気であり、診断名があります。
まず問診や診察を行います。問診では、患者さんのお悩みに寄り添いながらお話を伺います。診察では、血圧などの内科的なものから、脳神経系の異常の有無を調べる神経学的検査も必要に応じて行います。問診・診察の結果、脳MRI等の画像検査や血液検査が重要になることがあります。画像検査は、近隣の連携医療機関と連携をして検査依頼します。もし、既に他院で撮像されているMRIなどの脳画像などあるようでしたら、事前にそのデータを前医等からCDでご用意いただき、当院初診時にご持参下さい。重要な参考資料になります。
実際の診断名は片頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛など、脳画像等の診察や検査で異常が見られない頭痛(一次性頭痛)と、くも膜下出血や脳腫瘍などの脳疾患や副鼻腔炎などに伴う頭痛(二次性頭痛)があります。他にも多くの診断名があります。
② 治療
診断名に準じた治療を行っていきます。
診断時に、脳腫瘍など入院や手術が必要な患者さんは、信頼できる連携医療機関に依頼して治療をしていきます。
一次性頭痛の治療は、頭が痛い時に行う「急性期治療」と、頭痛の程度を軽くしたり頻度を少なくしたりする「予防治療」があります。「急性期治療」は、薬の内服する量やタイミングが大切になり、それを外来でお話します。一方、この治療だけでは頭痛の頻度は改善しません。頭痛は「予防治療」が重要です。頭痛の頻度が多い、頭痛の急性期治療のみで痛みがとり切れない方は予防治療の導入を検討していきます。
③ 治療中のサポート
治療の資料として大切なのは、頭痛の記録をつける「頭痛ダイアリー」です。受診時にお渡しします。患者さんに記載していただくことで、頭痛の頻度・強さ・誘因、急性期治療薬の効果等、頭痛の特徴を知ることができ、治療戦略を立てるのに重要な資料となります。また、急性期治療・鎮痛剤を飲みすぎているならその対策をたてる、頭痛の誘因が分かったらできるだけそれを避けて生活する等、この頭痛ダイアリーで知りえた情報で生活習慣もサポートしていきます。
頭痛の診療は、一度受診して終わりではありません。継続して診察を受けていただくことで、多くの頭痛が確実に良くなります。受診をやめないで根気よく通院していただきたいと思います。
いろいろな頭痛(頭痛の種類)
01片頭痛(診察や検査で異常がない一次性頭痛)
- 繰り返しおこる、中等度~重度の頭痛です。
- 片側の頭痛でなくてもよく、嘔気・嘔吐を伴うことがあります。
- 頭痛時に動くとつらいため、横になりたくなります。
- 人によっては、光や音、臭いなどに過敏になります。
頭痛時に暗くて静かな部屋で横になりたくなる人は片頭痛です。頭痛の持続時間は、数時間から長いと3日間程度続くこともあります。片頭痛の前兆として、頭痛発作前1時間以内に、キラキラ・ギザギザした模様が出現し次第に広がる「閃輝暗点」が出る方がいます。また予兆として、数時間~2日前ぐらいより、生あくびがでたり、イライラしたりすることもあります。20‐40歳代の女性に多く、月経中や前後・排卵時期に発作を起こすことがあります。お母さんお父さんから遺伝することもあります。
治療は、頭痛のときに治療する頓服の急性期治療が代表的であり、通常の鎮痛剤よりも効果のある片頭痛用の頓服薬もあります。
一方、片頭痛で大切なのは予防治療です。この治療法は、片頭痛の回数や持続時間を減らしたり、頭痛の程度を軽くしたりします。通常、バルプロ酸やプロプラノロール、アミトリプチリンなどの予防薬を毎日内服することで効果がみられます。
その他、2021年から本邦で使用できるようになった優れた効果が期待できるCGRP関連抗体薬(注射剤)があります。以下をご参照ください。
片頭痛予防の注射薬 CGRP関連抗体薬
- CGRPという片頭痛発作時に関係する物質の働きをブロックすることにより片頭痛の予防効果を示します。
- 治療適応は、内服予防薬で効果が不十分もしくは副作用で内服薬使用できない15歳以上の患者です。
- 効果は非常に高く、約半数の方が頭痛発作頻度が半分になり、約1割の方が頭痛が全くなくなります。
- 月に1回医療機関で皮下注射をします。通院が大変な方は、薬剤を処方し自宅にてご自身で注射する方法もあります。
- 副作用はとても少なく、注射部位の痛み・かゆみが出るかたが時にいらっしゃる程度です。
- 2025年1月現在3種類の薬剤があり、注射剤の多くが1本あたり40,000円前後と高価ではありますが、健康保険適応ですので3割もしくはそれ以下の自己負担です。
当院では多くの患者さんにこれらの薬剤を導入しており、ほとんどの患者さんが効果を感じています。「人生変わった」と言われる方もいらっしゃいます。
この薬剤の詳細は、当院ブログ(「片頭痛予防薬 CGRP関連薬剤」)もご参照ください。
02緊張型頭痛(診察や検査で異常がない一次性頭痛)
- 頭痛時に、嘔吐する、寝込むことはあまりありません。
- 動作で痛みの増強はなく鎮痛剤内服で落ち着くことが多いです。
- 頭痛部位を押すと、痛みが強くなります(圧痛)。
- 頭痛の持続時間は、1時間程度~一週間程度続くなど様々です。
緊張型頭痛は、一番多い頭痛であり、あまりつらい痛みではありません。「頭痛が心配だから」ということで受診されることが多いです。
治療は、痛いときにしっかり鎮痛剤などの頓服薬を使用することが大切です。痛みは放置しない、しっかりと薬で抑えることです。「痛みが軽いからいいや」と思い鎮痛剤を飲まないで我慢していると、頭痛が次第に慢性化していきます。特に頭痛薬を月に10日以上内服している場合は要注意です。自分でできる予防としては、ストレッチや入浴などで頭頚部のリラックス・血流改善などでよくなることがあります。また医療機関での予防治療は、頭痛体操などの理学療法、アミトリプチリンなどの予防内服薬などがあります。
03群発頭痛(診察や検査で異常がない一次性頭痛)
「三叉神経・自律神経性頭痛」とも言います。
- 片側の目の周囲や側頭部にかけての、かなり強い痛みです。
- 持続時間は15分~3時間程度です。
- 痛い側の目が充血、涙が出る、鼻がつまるなどの併存症状。
- 頭痛時は静かにじっとできず、興奮した様子で動き回ります。
群発頭痛は、頓服薬や頓服の注射剤があります。この注射剤は自宅で使用できる自己注射という方法もあります。また予防治療として、いくつか内服薬があります。とても痛い頭痛なので、患者さんにあった治療法を、我々と一緒に考えていきます。
04薬物乱用頭痛
薬物乱用頭痛とは、もともと片頭痛などの頭痛がある人が、頭痛薬を内服する量が増えていくうちに薬が効きにくくなり、頭痛を強く感じやすくなった状態のことを言います。頻回に頭痛があるのでそのたびに薬を飲む、また頭痛がでるのが嫌なので予防的に痛み止めを内服してしまう、という患者さんに薬物乱用頭痛がおきやすいです。
月に頭痛が10日以上あり、そのたびに鎮痛剤を内服している人は要注意です。このような方は、早めにご相談ください。
外来では頭痛ダイアリーで頭痛の頻度と内服状況を確認します。そして使用している薬を減量→中止、もしくは他の薬剤に変更、また頭痛の予防する生活習慣の指導や内服薬の処方を行っていきます。
05その他の頭痛
1~4以外の頭痛にも、様々な原因があります。これらの頭痛も、診察や検査などで的確に診断・治療に結び付けます。
◯くも膜下出血(SAH)
◯脳腫瘍
◯副鼻腔炎
◯椎骨動脈解離
◯可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)
◯低髄圧症候群
等
当院で診療できる頭痛
片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、薬物乱用頭痛、そのほか様々な頭痛がありますが、入院や手術・特殊な脳の治療が必要なケース以外は、当院で診療が可能です。



